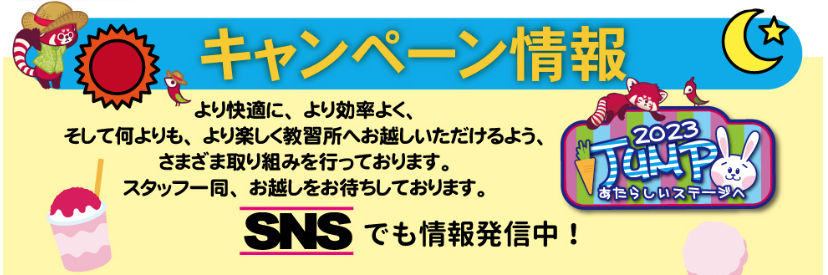準中型免許にAT限定免許新設へ! 2026年より導入予定
2026年より準中型免許に「AT限定免許」が新設される予定です。トラックやバスのAT車が普及している現状や、職業ドライバーの慢性的な不足といった状況を踏まえた決定で、今後はAT車のみの操作で準中型免許を取得することが可能です。
これにより「配送ドライバーに興味はあるけど、MT車の運転はちょっと不安……」と感じている方でも運転しやすくなり、職業ドライバーへの間口が広がることとなります。
この記事では、導入予定の準中型AT限定免許について、導入される背景や影響なども含めて、詳しく解説。免許取得への第一歩を後押しします。
目次
新たに登場する準中型AT限定免許とは?
2026年から準中型免許に「AT限定免許」が新設されます。
従来、職業ドライバーになるためには、MT免許を取得しなくてはなりませんでした。AT限定免許を新設することで、免許取得のハードルを下げ、慢性的な人手不足の解消につなげるのが大きな狙いです。
トラックやバスのAT車が普及している現状も鑑みての決定で、導入されれば、教習生はAT車のみの運転で準中型免許の取得が可能となります。
今後、運送業界をはじめ「職業ドライバー」が求められる業界で、AT車を運転できる人材の確保がしやすくなり、ドライバー不足の緩和につながると期待されています。
運転できる車両の範囲
新設される「準中型AT限定免許」では、準中型免許の対象となる車両のうちAT車のみを運転できます。
準中型免許で運転可能な車両の範囲は、以下の通りです。
・車両総重量:3.5t以上7.5t未満
・最大積載量:2t以上4.5t未満
・乗車定員:10人以下
準中型AT限定免許を取得すれば、上記範囲内のAT車両を運転可能になります。
具体的には、コンビニなどのルート配送車や引っ越し用のトラック、クール宅急便などの保冷設備のあるトラック、高所作業車、ゴミ収集車などが当てはまります。
準中型AT限定免許が導入される背景
準中型AT限定免許が新たに導入されるには、以下のようなさまざまな背景があります。
・物流業界が直面している課題
・AT車の普及
・運転免許取得の間口拡大
・多様なドライバー層の活躍促進
どのような背景があるのか、それぞれ解説します。
物流業界が直面している課題
準中型AT免許が新設される大きな理由として、物流業界が直面している深刻な課題「人手不足」が挙げられます。
特にトラックやバスの運転手は、長年にわたり慢性的な人手不足の状態です。2020年度時点で、営業用トラックドライバーは4.6万人不足しているとされており、2030年度にはさらに21.4万人不足すると予測されています(※1)。
輸送能力においては、2024年には14.2%・2030年には34.1%不足する可能性があると試算されており、荷物が届かない・即日の宅配サービスが受けられないなどの問題が発生する見込みです(※2)。
こうした人手不足に拍車をかけるのが「2024年問題」。働き方改革関連法により時間外労働の上限規制が適用されることで、ドライバーの労働時間・走行距離が短縮され、輸送力の低下・運送コストの上昇が懸念されています。
また近年、若者の免許取得は圧倒的にAT限定が人気ですが、物流業界ではいまだMT車が主流であったため、若年層の採用が難しくなってきています。
免許取得の壁を下げることで、深刻な人手不足の解消につなげようと、準中型AT限定免許が導入されることとなりました。
※参考1:株式会社NX総合研究所.「「物流の2024年問題」の影響について(2)」.(参照2025-06-09)
※参考2:全日本トラック協会.「知っていますか?物流の2024年問題」.(参照2025-06-09)
AT車の普及
近年は乗用車だけでなく、トラックやバスなどの大型車両においてAT車の普及が進んでいるのも、準中型AT免許が新設される理由の一つです。
実際、日本自動車工業会の調査によると、運輸業界が2022年に保有する車両の34%がAT車になっているほど。日本自動車販売協会連合会や警察庁による聞き取りでは、2023年に販売された大型バスの約9割・大型トラックの約7割がAT車で、運輸事業者の多くが今後もAT車の保有を増やす意向となっています(※)。
AT車の普及が拡大している理由として、下記の点が挙げられます。
・MTよりも運転が簡単で、初心者でも扱いやすい
・操作ミスが少なく、トラブル発生のリスクを軽減できる
・渋滞時などのクラッチ操作が不要で、運転のストレスが軽減される
・技術進歩で、トラック向けの高性能なAT車が開発された
大型車両においてもAT車が普及している状況を踏まえて、免許制度も実態に合わせて見直す必要が生じました。
※参考:朝日新聞.「大型や中型の免許にAT車限定免許導入へ 2024年問題解消に期待」.(参照2025-06-09)
運転免許取得の間口拡大
準中型AT限定免許の新設は、運転免許取得のハードルを下げ、より多くの人が免許を取得しやすくする間口拡大の意味合いもあります。
複雑な操作が必要ないAT車は、MT車に比べて運転操作が簡単なため、複雑なクラッチやギア操作など、運転技術の習得に不安を感じていた人でも挑戦しやすくなります。
実際、2025年4月からは普通自動車のMT免許取得も、基本的な教習や卒業検定はAT車で行われるようになるため、MT車の操作に関する教習は限定的になりMT免許取得のハードル自体が従来より下がる見込みです。
新制度では、AT車のみで教習や検定が完結するため、運転初心者でもスムーズに免許を取得できる環境が整い、免許取得の間口が広がると期待されています。
多様なドライバー層の活躍促進
準中型AT限定免許の導入により、免許取得がしやすくなることで、物流業界をはじめ職業ドライバーへの新規参入者を増加させられると期待されています。
MT車は複雑な操作が必要になるため、AT限定が新設されれば、これまでMT車の操作に不安を感じていた人や、MT免許取得のハードルが高いと感じていた層も、挑戦しやすくなります。
ドライバーになるハードルを下げ、性別・経験・年齢を問わず、職業ドライバーに挑戦できる環境の整備を目指しているのが現状です。
これまでMT免許の取得者は、一般的に男性の割合が多い傾向にありましたが、女性・高齢者など多様な人材が物流業界で活躍できる可能性を広げられれば、ドライバー不足解消の一助になるでしょう。
また、まずはAT限定で運転可能な車両からスタートして、本人の希望に応じて限定解除・上位免許取得を目指すなど、多様な働き方を支援する動きも見られます。
いつから始まる? 準中型AT限定免許の施行時期
準中型AT限定免許が、いつから施行されるのか具体的な時期を紹介します。
また、トラックやバスのAT車の普及・職業ドライバー不足といった状況を踏まえて、準中型以外にも大型免許・中型免許および大型・中型第二種免許にも「AT限定免許」が新たに導入されます。
新制度の施行時期は免許の種類によって異なるので、こちらも併せて見ていきましょう
準中型AT限定免許の施行予定日
準中型AT限定免許の施行予定日は、2026年4月1日です。
2026年4月1日から、準中型免許のAT限定の教習を受けられるようになり、AT車のみの教習・試験で免許取得を目指せるようになる見込みです。
ただし、準中型AT限定免許の教習を行うかどうかは教習所によって異なります。現在、準中型教習を行っている教習所でも、準中型ATの教習車を新たに導入する必要があるため、すぐにはAT限定の教習を実施していないことも考えられます。
教習所に通う前に、準中型AT限定免許に対応しているか確認が必要です。
他の免許区分(中型・大型・二種)の導入スケジュール
準中型免許以外のAT限定免許の導入スケジュールは、以下の通りです。
・中型・中型第二種免許:2026年4月1日
・大型免許:2027年4月1日
・大型第二種免許:2027年10月1日
まずは、普通免許・普通二種免許のAT限定に関わる試験・教習方法の見直しが、2025年度に先行して実施されます。その後、順次中型・中型二種、大型・大型二種が施行される予定です。
準中型AT限定免許の導入により期待される効果や運輸業界への影響
準中型AT限定免許の導入により、運輸業界はもちろん個々のドライバーに至るまで、広範囲な影響が予想されています。
どのような影響があるのか、期待されている効果を解説します。
ドライバーの労働環境が改善する
準中型AT限定免許の導入によって、運輸業界で深刻化している人手不足の解消が期待されます。
AT限定免許の導入によりトラックの免許取得ハードルが下がれば、より多くの人材を採用しやすくなる見込みです。採用できる人材が増えることで、これまで一部のドライバーに集中していた長時間労働の負担が分散され、労働時間の短縮や休息の確保など、トラックドライバーの負担が軽減されると期待されます。
また、AT車はMT車よりも操作が簡単なため、長時間運転によるドライバーの身体的・精神的な疲労が軽減される点も大きなメリットです。
AT車の普及で労働時間・疲労が軽減され、現在の過酷な労働環境が改善されていくと考えられます。
多様な人材が働きやすい環境が求められる
準中型AT限定免許の導入によりドライバー職の間口が広がることで、新たに女性や高齢者などの参入が期待されているため、多様な人材が働きやすい環境が求められます。
性別や年齢を問わずに、誰もが働きやすい職場環境づくりが一層重要です。例えば、女性用のトイレや更衣室の改修、ライフスタイルに合わせた柔軟な勤務体系の導入、社内での女性同士のサポート体制の構築などが挙げられます。
また高齢者に対しては短時間勤務や健康管理の強化、長距離運行や手積み・手卸の少ない体力的負担が抑えられる業務への配置などの配慮が必要でしょう。
こうした「働きやすさ」を整えることで、新しい人材確保・定着率向上はもちろん、既存ドライバーの働き方改革やモチベーションアップにもつながります。
キャリアプランが多様化する
準中型AT限定免許で、運送業界に参入できるようになったことで、ドライバーのキャリアプランが多様化すると考えられます。
今まではMT車の免許を取得してドライバーになる道しかありませんでしたが、今後はAT限定でスタートして、慣れてきたら限定解除してMT車も運転できるようになるという段階的な成長が可能です。
運輸業界でもAT車の割合が増えつつあるとはいえ、まだまだMT車の割合が大きいため、限定解除してMT車を運転できるようになれば、担当できる業務の幅が広がりキャリアアップになります。
MT車になじみのない若年層や女性など新たな人材の参入促進につながり、業界全体の活性化にもつながる見込みです。
新たな業務体制の整備が求められる
準中型AT限定免許の導入により、業務体制の整備も求められます。
AT限定免許取得者の採用が増えることで、従来のMT車中心の運用から変化が余儀なくされるため、AT車の活用を前提にした業務体制への転換が必要です。
例えば、以下のようなことが考えられます。
・AT車の新規導入
・導入したAT車の車両管理方法の見直し
・積載重量の確認や安全運行・法令順守の徹底
・AT限定免許取得者向けの研修・サポート体制の整備
・SNSや自社サイトの活用など採用活動の見直し
特に、AT限定免許を取得したばかりの業界経験の浅い人材を採用していくことに備える必要があるため、これまで以上に基本的な運行管理や教育体制の強化が不可欠です。
今後の安定した人材確保と安全運行の両立を実現させるために、業務体制の見直しが求められます。
まとめ
物流業界をはじめ、多くの業界で職業ドライバーが不足していることや、AT車が広く普及している状況を鑑みて、新たな人材を獲得できるように「準中型AT限定免許」が2026年から新設されることになりました。
AT限定が増えることで、これまでよりも運転・免許取得のハードルが低くなり、より広い層からトラックやバスのドライバーを確保できると考えられています。
しかし、どこの教習所でも免許を取得できるわけではありません。AT限定用の車両を用意する必要があるなど、教習所側で準備を整える必要があるからです。
インストラクター/車両数が地域No.1の武蔵境自動車教習所は、定休日なしでJR中央線武蔵境駅から徒歩5分という通いやすい環境が整っており、都内初のオンライン学科導入校でもあります。
準中型車の免許を取得して、手に職を付けたい方は「武蔵境自動車教習所」をチェックしてみてください。
Contactお問い合わせ
お気軽に
お問い合わせください
※電話受付:9:00~21:00(日曜のみ 9:00~19:00)
まずは、
料金シミュレーションを
してみる
プランの費用が確認できます!
まだ受講を迷っている方、ぜひ一度料金シミュレーションをし、ご自身が受講したい運転免許の費用をご確認ください。