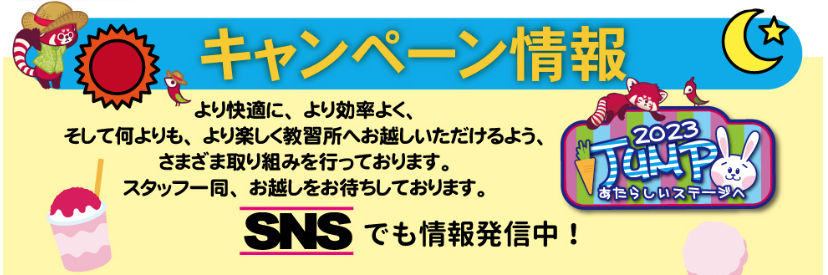AT限定免許とは? MT免許との違いや中型・大型車の免許取得について紹介
将来的に中型・大型(四輪)免許の取得を検討している方の中には、AT限定免許とMT免許どちらを選ぼうか悩んでいる方もいるでしょう。
免許取得には時間的・金銭的コストがかかるため、後悔のないよう失敗しない選択をしたいものです。2025年4月以降は、MT免許を取得する人もAT車による教習が行われるため、両者の違いを知っておくと選択しやすくなるでしょう。
そこでAT限定免許とMT免許の違いや運転できる車両、中型・大型免許取得への影響を解説します。AT限定免許とMT免許のどちらが良いか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
将来的には中型・大型車(四輪)のAT限定免許が登場
2025年現在、AT限定免許は普通自動車のみに適用されていますが、将来的には中型・大型車にも拡大される見込みです。
警察庁は今後、道路交通法施行規則などを改正して、2026年度以降に順次中型・大型車にもAT限定免許を導入する方針を固めています。
具体的には、免許の種別に応じて下記の区分が新設される予定です。
・貨物運送:AT大型、AT中型、AT準中型の3区分
・旅客運送:AT大型、AT中型の2区分
免許区分ごとの規定は下記の通りです。
| 貨物運送(車両総重量) | 旅客運送(乗車定員) |
| ・AT大型:11t以上 ・AT中型:7.5~11t未満 ・AT準中型:3.5~7.5t未満 |
・AT大型2種:30人以上 ・AT中型2種:11~29人 ・AT普通2種・普通2種:10人以下 |
この改正により、AT限定免許の適用範囲が広がることで、より多くの人が中型・大型車を運転しやすくなります。
中型・大型車(四輪)にAT限定免許が導入される背景
普通車にのみ適用されてきたAT限定免許が、中型・大型車にまで適用されようとしている背景として、深刻なドライバー不足・車両のAT化の2つが挙げられます。
なぜ中型・大型車にも、AT限定免許が導入されるのか、その背景を解説します。
ドライバーの人手不足
公共交通機関・運送業界では、バスやトラックを運転するドライバーの人手不足の深刻化が続いており、少しでも参入障壁を下げるための施策として、中型・大型車のAT限定免許が導入されようとしています。
実際、トラック運転手は1995年からの20年間で約21万人も減少しており、2015年~2030年までに約25万人減る可能性があるといわれています。バス運転手も同様で、2030年には約3万6,000人が不足する見通しです(※)。
この状況に拍車をかけるのが2024年問題です。2024年問題では、時間外労働の上限規制適用により、労働力がさらに不足すると予想されています。2019年4月から段階的に施行されてきた働き方改革関連法ですが、慢性的な人手不足が続いていた公共交通機関・運送業界では、施行に猶予が設けられていました。
この猶予が2024年までだったことから、今後ドライバーがさらに不足するといわれています。
中型・大型車にAT限定免許を導入することで、従来のマニュアル車操作技術の習得という高いハードルを下げて、多様な人材が参入しやすい環境を整えようとしています。
※参考:読売新聞.「オートマ限定免許、大型2種などにも導入へ…運転手不足へ対応」.(参照2025-01-30)
車両のAT化
多くの車両がAT化しており、MTの需要が大きく低下しているのも背景にあります。かつてはトラックやバスなど中・大型車両はMT車のみなのが当たり前でしたが、現在ではAT車が増えてきています。
日本自動車工業会による調査では、運輸業界が2022年に保有していた車両の34%がAT車でした。また、日本自動車販売協会連合会や警察庁による聞き取りでは、2023年に販売された大型バスの約9割・大型トラックの約7割がAT車でした(※)。
メーカーや運輸事業者の多くが、今後もAT車の生産・保有を増やす意向のため、さらにAT車が増えMT車は減少する一方であると考えられます。
こうしたAT車が増加している理由の一つとして、MT運転技術の需要自体が減少していることが挙げられます。AT車は操作が簡単で、渋滞時のストレスもMT車より軽減されるため、運転手の負担が軽く、トラック・バス業界のドライバーからも歓迎されやすいのです。
※参考:朝日新聞.「大型や中型の免許にAT車限定免許導入へ 2024年問題解消に期待」.(参照2025-01-30)
普通車のAT限定免許とは?
そもそもAT限定免許とは、オートマチック限定免許の通称です。普通車のAT車に限り運転できる限定条件付きの普通自動車免許のことです。
AT車には自動変速機が搭載されており、ドライバーがアクセルを踏むだけで、自動でギアチェンジしてくれます。シフトチェンジやクラッチペダルなどの操作も必要ないため、操作がシンプルで、誰でも運転しやすくなっているのが特徴です。
AT限定免許を取得していれば、普通自動車(AT)はもちろん、小型特殊自動車や原付も運転できます。
AT限定免許とMT免許の違い
AT限定免許とMT免許の大きな違いは、運転できる車両が異なることです。MT免許はマニュアル車(MT)だけでなく、AT車や小型特殊自動車、原付も運転できるため、AT限定免許よりも運転できる車の幅が広くなっています。
運転の操作性の違いとしては、MT車はシフトレバーやクラッチペダルを運転手が操作して、自分でギアチェンジする必要があります。
自分で車を操作できる面白さがあるものの、操作が複雑で覚えにくく、また慣れるまではエンストを起こしやすいなど、AT車よりも習得ハードルが高いのが特徴です。
AT限定免許ができた理由
車の機能が進歩するに伴い、変速機がMTからATに変わっていったことや、より多くの人が運転しやすい気軽さから、AT車が普及していきました。AT車の需要が拡大していくことで、1991年にAT限定普通免許が導入されます。
現在では、国産自動車の新車に占めるAT車の比率は、ほぼ100%に近づいており、MT車に乗車する機会はほとんどなくなりつつあります。
AT限定免許とMT免許はどちらの取得率が高い?
AT限定免許とMT免許では、圧倒的にAT限定免許を取得する人が多くなっています。
実際、2022年時点の普通免許(二種含む)を取得した約119万人の内、AT限定免許の取得者は73%と過半数を占めていました(※)。
一部のスポーツカーや商用車を除いて、新たに発売される車のほとんどがAT車ということもあり、基本的にはAT限定免許を取得する人が多い傾向にあります。「運転したい車がMTのみ」「仕事で使う」などの理由がない限りは、AT限定でも問題ないでしょう。
※参考:警察庁交通局運転免許課.「運転免許統計」.(参照2025-01-30)
AT限定免許で運転できる車両
AT限定免許で運転できる車両は、下記の通りです。
・普通自動車(AT車のみ)
・小型特殊自動車
・原付(原動機付自転車)
2024年1月現在は、トラックをはじめとした中型・大型車(四輪)は運転できません。
ただし前述したように、2026年度以降の法改正により、準中型・中型・大型も段階的にAT限定免許が導入されます。
また、2025年4月1日からは、MT免許を取得する場合は、まずAT車での教習を受けるかたちに変更になります。AT車での教習を修了して卒業証明書を受け取ったら、そのままAT限定解除の教習(最短4時限)を受けるため、従来のAT限定解除と同じような流れです。
そのため試験場へは、AT限定解除の卒業検定の分と併せて、2枚の卒業証明書を持って行くことになります。
教習原簿の電子化により免許の取得が簡単に
教習原簿が電子化されたことにより、従来よりも免許の取得が簡単かつ効率的になっています。
従来は、教習生の個人情報や教習状況を記録する「教習原簿」が紙だったため、持ち歩きの手間や紛失のリスク、教習所外で確認できない不便さなど、さまざまなデメリットがありました。
教習原簿が電子化されることで、スマートフォンから簡単に確認できるようになり、教習状況を確認しやすくなってスケジュールが立てやすかったり、教習所によっては質問やフィードバッグができたりと、効率的に教習を受けられるようになります。
武蔵境教習所では、2024年6月から都内で初めて教習原簿の電子化を導入しており、より快適に教習を受けられるようになっています。
まとめ
AT限定免許ではMT車を運転できませんが、流通しているほとんどの車両はAT車のため、特別な事情がない限りAT限定免許の取得でも問題ありません。
近年ではバスやトラックのような中型・大型車にもAT車が普及してきており、今後さらに増加していく見込みのため、2026年以降には中型・大型車免許にもAT限定免許が導入される予定です。
免許取得を考えているなら武蔵境教習所をご検討ください。教習原簿の電子化により効率的に免許取得を目指せるだけでなく、JR中央線武蔵境駅から徒歩5分・定休日なしで平日21時まで営業と、通いやすい立地・環境が整っています。
資料はすぐにダウンロードできるので、まずはお気軽にご請求ください。
Contactお問い合わせ
お気軽に
お問い合わせください
※電話受付:9:00~21:00(日曜のみ 9:00~19:00) 【教習中の方は専用ダイヤルをご利用ください】
7:30~21:00(日曜のみ7:30~19:00)
まずは、
料金シミュレーションを
してみる
プランの費用が確認できます!
まだ受講を迷っている方、ぜひ一度料金シミュレーションをし、ご自身が受講したい運転免許の費用をご確認ください。