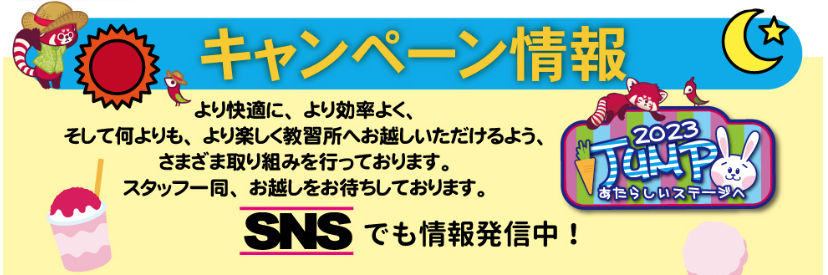人材開発支援助成金は車の免許取得に利用できる? 対象の自動車免許や申請方法を解説!
多くの業界で人手不足が叫ばれている中、特に物流業界をはじめとするドライバー不足は多くの企業にとって喫緊の課題でしょう。そこで注目が集まっているのが「人材開発支援助成金」です。
人材開発支援助成金は、高額になりがちな運転免許の取得費用に、助成金を活用できます。そのため自社のドライバーの運転免許取得に助成金を活用したい企業や、雇い主から運転免許を取得するよういわれた従業員の金銭的負担を軽減することが可能です。
そこで本記事では、人材開発支援助成金の対象となる免許の種類や、具体的な申請方法について詳しく解説します。企業の採用担当者・経営者はもちろん、これから免許取得を目指す従業員の方も必見の内容なので、ぜひ参考にしてみてください。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)とは?
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)とは、企業が従業員に対して、職務に必要な知識や技能を身に付けさせるため計画的に職業訓練などを実施した場合に、訓練経費・訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です(※)。
助成金の中には内容に応じて、以下4つのコースがあり、自動車免許の取得は「人材育成支援コース」で申請可能です。
・人材育成支援コース
・教育訓練休暇等付与コース
・人への投資促進コース
・事業展開等リスキリング支援コース
例えば、人材育成支援コースの場合は「10時間以上のOFF-JT」「新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練」「有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練」など幅広い訓練が対象となります。
助成対象となるのは事業主・事業主団体などで、対象労働者は雇用保険被保険者のため、正規・非正規の従業員を問いません。
ただし助成金の支給に当たっては、厳正な審査が行われます。審査に通らないと助成金を得られないのはもちろん、確認項目が多いため他の助成金よりも支給可否の決定までに時間がかかることから、早めの申し込みが必要となります。
※参考:経済産業省.「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」.(参照2025-06-30)
対象となる自動車免許
人材開発支援助成金の対象となる自動車免許は、以下の通りです。
| 対象となる免許 | 運転できる車両 |
| 中型免許 | 4tトラック、マイクロバス など |
| 準中型免許 | 2tトラック、3tトラック など |
| 大型免許 | ダンプカー、大型バス など |
| 大型特殊免許 | ショベルカー、ホイールローダー など |
| けん引免許 | トレーラー など |
| 二種免許 | タクシーや運転代行など、旅客運送のための車両 |
一方で、普通自動車免許や二輪免許の取得を目的とした教習や、業務に直接関係しない場合の取得、適性検査は助成の対象外です。
人材開発支援助成金を受け取るための条件
人材開発支援助成金を受け取るための条件として、「被保険者が対象の訓練の場合」と「有期契約労働者が対象の訓練の場合」の2パターンがあり、条件内容が異なります。
それぞれ、どのような条件があるのか解説します。
被保険者が対象の訓練の場合
被保険者が対象の訓練の場合、下記のような条件をクリアする必要があります。
1.雇用保険適用事業所の事業主であること
2.労働組合などの意見を聞き、事業内職業能力開発計画を作成して内容を労働者に周知していること
3.事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画届を作成し、内容を被保険者に周知していること
4.職業能力開発推進者を選任していること
5.職業訓練実施計画届に基づき、雇用する被保険者に訓練を受けさせる事業主であること
6.雇用する被保険者を事業主の都合により解雇した事業主以外の事業主であること
7.特定受給資格者の数が一定の割合を超えている事業主であること
8.職業訓練期間中も適正な賃金を支払っていること
9.必要な書類を整備し、5年間保存していること
10.審査に必要な書類などを提出し、実地調査に協力すること
11.定期的なキャリアコンサルティングを実施することを事業内職業能力開発計画などで定めていること
※参考:厚生労働省.「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」.(参照2025-07-09)
有期契約労働者が対象の訓練の場合
有期契約労働者が対象の訓練の場合、下記のような条件をクリアする必要があります。
1.雇用保険適用事業所の事業主であること
2.有期契約労働者などを雇用、もしくは新たに雇い入れる事業主であること
3.対象労働者に対して職業訓練実施計画届を作成し、管轄労働局長へ提出していること
4.職業訓練実施計画届に基づき、雇用する有期契約労働者などに有期実習型訓練を受けさせること
5.計画を実施した事業所で雇用する被保険者を解雇など事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること
6.特定受給資格者の数が一定割合を超えている事業主であること
7.訓練期間中も適正な賃金を支払っていること
8.必要な書類を整備し、5年間保存していること
9.審査に必要な書類などを提出し、実地調査に協力すること
被保険者が対象の訓練とは違い「定期的なキャリアコンサルティングの実施」が定められていないなど、細かな部分が異なります。
※参考:厚生労働省.「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」.(参照2025-07-09)
助成金額
人材育成支援コースの助成額・助成率は、以下の通りです。
| 支給対象者 | 助成率 | 賃金助成(1人1時間当たり) |
| 雇用保険被保険者の場合 | 45%(30%) | 760円(380円) |
| 有期契約労働者などの場合 | 60% | |
| 正規雇用労働者などへ転換した場合 | 70% |
※( )内は中小企業以外の助成額・助成率
(※1)
同じ人材育成支援コースであっても、支給対象者や企業の規模によって助成率は30~70%と異なります。
また受講者1人1訓練当たりの上限金額は、以下の通りです。
| 企業規模 | 10時間以上100時間未満 | 100時間以上200時間未満 | 200時間以上 |
| 中小企業事業主 事業主団体など |
15万円 | 30万円 | 50万円 |
| 中小企業以外の事業主 | 10万円 | 20万円 | 30万円 |
(※2)
また、1つの事業所または事業主団体が1年度当たりに受けられる助成金の限度額は、1,000万円と決められています。
※1 参考:厚生労働省.「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」.(参照2025-06-30)
※2 参考:山口労働局職業安定部職業対策課.「社員の中型免許・大型免許等の取得に助成金を活用できます!」.(参照2025-06-30)
人材開発支援助成金の申請方法
ここからは、どのように人材開発支援助成金を申請すればいいのか、具体的な方法を解説します。
職業能力開発推進者を選ぶ
まずは、自社内で研修・訓練を推進する「職業能力開発推進者」を選びましょう。
職業能力開発推進者は「事業内職業能力開発計画の作成・実施」や「職業能力開発に関する労働者への相談・指導」などを行います。
選任に当たっては、下記のポイントを押さえておくことが大切です。
・事業内職業能力開発計画の作成・実施や、労働者への適切な相談・指導が行える
・労務・人事担当部課長など、従業員の職業能力開発および向上に関する企画・訓練の実施権限を有する
・事業所ごとに1名以上の推進者を選任する
事業内職業能力開発計画を作成する
推進者を選定できたら、自社の人材育成の基本的な方針などを記載する「事業内職業能力開発計画」を作成しましょう。
作成時には、経営者・管理者と従業員が共通認識を持って目標に進めるよう、育成の目的や到達目標、実施時期、方法などを具体的に示します。例えば、どの職種にどのようなスキルを身に付けさせるか、どのタイミングで研修を行うかなどを記載しましょう。
従業員は自身の成長イメージを持ちやすくなり、目標に向かって主体的に学習・訓練に取り組む意欲が高まると期待されます。
作成した計画は従業員に周知し、職務に必要な能力・自社の育成方針について共有しましょう。
訓練実施計画届を提出する
訓練開始日の1カ月前までに「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」と下記の必要書類を、事業所ごとに各都道府県労働局へ提出します。
・訓練別の対象者一覧(様式第3号)
・人材開発支援助成金 事前確認書(様式第11号)
・事業所確認票(様式第14号)
・雇用契約書(写)など、訓練対象者が雇用されていることが確認できる書類
・キャリアコンサルティングについての規定が確認できる書類
・訓練の実施内容などを確認するための書類 など
提出後、内容に変更が生じた場合は速やかに変更届を提出する必要があります。
手続きは雇用保険の適用事業所単位で行い、提出期限を過ぎると助成金の対象外となるため、事前準備とスケジュール管理が重要です。
計画書の通りに訓練を実施する
計画書に記載した通りに、訓練を実施します。
人材育成支援コースの訓練には、人材育成訓練・認定実習併用職業訓練・有期実習型訓練の3つがあり、免許取得は人材育成訓練が該当します。
人材育成訓練では、職務に必要な専門知識や技能を身に付けるための座学や実技など、OFF-JT訓練に対する助成金です。実質的な訓練時間が10時間以上かつ、対象者の訓練受講時間が上記時間の8割以上であることが要件です。
訓練の実施状況は、出席簿や受講記録などで証明できるように管理し、計画と実際の訓練内容にずれがないようにする必要があります。
支給申請書を提出する
訓練終了の翌日から2カ月以内に、支給申請書(様式第4号)と、下記の必要な書類を労働局へ提出します。
・支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
・支払方法・受取人住所届
・人材開発支援助成金 支給申請書(様式第4号)
・賃金助成およびOJT実施助成の内訳(様式第5号)
・経費助成の内訳(様式第6号)
・OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号) など
申請先は、事業所または事業主団体などの事務所所在地を管轄する労働局です。ただし都道府県によっては、ハローワークでも受け付ける場合もあるため要確認です。
審査を待ち、助成金を受け取る
必要書類を提出できたら、労働局による審査を待ちます。提出した書類や訓練の実施状況などが確認され、不備や疑義があれば追加資料の提出を求められる場合があります。
審査には一定の期間がかかるため、申請から実際に助成金を受け取るまでには時間がかかることに注意が必要です。
審査を通過し支給が認められると、指定した口座に助成金が振り込まれます。
人材開発支援助成金を免許取得に利用するメリット
人材開発支援助成金を免許取得に利用することで、大きく3つのメリットを得られます。どのようなメリットがあるのか、それぞれ解説します。
低コストの人材育成がかなう
人材開発支援助成金を免許取得に活用することで、従業員育成にかかる費用負担を軽減できる点は大きなメリットです。
免許取得をはじめ研修や訓練には、受講料や教材費、訓練期間中の従業員の賃金など多くの金銭的コストが発生します。助成金を利用すれば、免許取得にかかる経費・賃金の一部が助成され、訓練内容やコースによっては、費用の最大70%も助成されるケースもあります。
企業の自己負担を最小限に抑えられるため、従業員数が多い場合や複数名の育成を同時に進める場合でも、総額の負担を大幅に減らすことが可能です。費用面で導入をためらっていた企業でも、積極的に人材育成に取り組めます。
生産性の向上に寄与する
人材開発支援助成金の活用で、従業員が免許の取得によりスキルアップすることで、より生産性高く業務を遂行できるようになります。
例えば、必要な免許の取得で作業の幅が広がることで、従来は外部へ委託していた業務を社内で完結できるようになり、時間・費用といったコストの削減につながります。
また、外部に委託するために発生していた業務や、外部業者が到着するまでの待ち時間など、余計なコストを省いてスピーディーに動けるのもメリットです。
企業と従業員両者の成長につながる
人材開発支援助成金で免許取得を支援することで、企業・従業員の双方に成長の機会が生まれます。
企業側は、従業員の専門知識・技能が向上することで、業務効率・生産性が向上。より質の高いサービスや商品を提供できるようになり、売上アップにつなげやすくなります。
一方、従業員は免許取得を通じて自らのスキルを高められることで、業務の幅が広がるだけでなく、キャリアアップへの意欲も増します。新たな知識や技術の習得は仕事への自信や達成感につながり、モチベーション向上にも直結するものです。
結果として、従業員の定着率や採用力も強化され、企業の持続的な成長を支える基盤となります。
人材開発支援助成金を利用する際の注意点
人材開発支援助成金には、いくつか押さえておきたい注意点があります。それぞれ解説するので、事前に把握しておきましょう。
申請に手間と時間がかかる
申請に手間と時間がかかるので、すぐには助成金を得られない点には注意しましょう。
助成金の申請のために、いくつか必要書類を用意したり、担当者を選定したりと手間がかかるため、どうしても時間がかかってしまいます。スムーズに申請できたとしても、審査にも時間がかかるため、審査待ちの期間も考慮して早めに申請する必要があります。
また申請には提出期限が定められているので、日常業務が忙しい中でも計画的に進められるように、スケジュールを逆算して準備を始めることも大切です。
コースごとに要件が異なる
人材開発支援助成金は複数のコースが用意されており、それぞれ支給要件や対象となる訓練内容、申請手続きが異なるため、間違った内容で準備を進めないよう注意しましょう。
例えば正社員向けと有期契約労働者向けでは、必要な訓練の種類・助成対象となる条件が異なります。
さらに、申請要件は年度ごとに見直しや変更、新設、廃止が行われることもあるため、前年と同じ内容で申請すると要件を満たさないかもしれません。
実際、2023年4月には複数の訓練コースが統合され、新たに「人材育成支援コース」として再編成されました(※)。このようにコースの内容や要件は流動的なため、最新の制度内容を厚生労働省の公式情報を必ず確認しましょう。
※参考:厚生労働省.「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」.(参照2025-06-30)
必ず支給されるとは限らない
申請したからといって、必ず支給されるとは限らない点には注意が必要です。
人材開発支援助成金の交付決定は、訓練終了後に行われるため、訓練にかかる費用を立て替えなければならない上、審査に落ちれば支給されません。
審査では、計画や実施内容が要件を満たしているか、証拠書類が正確かなど厳しく確認されるので、訓練を実施したのに助成されずコストだけかかることがないように、必要な要件や書類を確実に整えることが重要です。
まとめ
人材開発支援助成金は、高額になりがちな運転免許の取得費用を軽減してくれるもので、自社従業員の運転免許取得をサポートしたい企業の心強い味方です。
自動車免許の取得は「人材育成支援コース」で申請可能で、大型免許や中型免許、けん引免許など、業務に直接関与する免許の取得に活用できます。
こうした業務に関連する免許の取得には、武蔵境教習所がおすすめです。JR中央線武蔵境駅から徒歩5分で平日は21時まで営業と、仕事帰りに通いやすく、働きながらでもスキルアップしやすい環境です。まずは気軽に、資料請求をお問い合わせください。
Contactお問い合わせ
お気軽に
お問い合わせください
※電話受付:9:00~21:00(日曜のみ 9:00~19:00)
まずは、
料金シミュレーションを
してみる
プランの費用が確認できます!
まだ受講を迷っている方、ぜひ一度料金シミュレーションをし、ご自身が受講したい運転免許の費用をご確認ください。